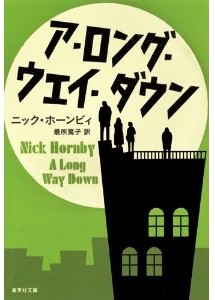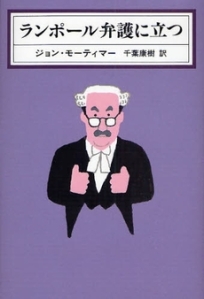絶望的な時間のなさに悩まされる今日このごろ。
本を読んでこそはいるものの、逐一感想を書くのは諦めるしかなさそうだ…嗚呼。
6月にはもう少しペースを上げたいのだけれど、どうなることやら。
『アバウト・ア・ボーイ』『17歳の肖像』の著者によるポップなヒューマンドラマ作品である。
描かれているのはまさにイギリスそのものというか、ロウワーミドルからワーキングクラスのイギリス人にとって等身大のイギリスとはこういうものだということがありありとわかる。現代文学に於いて風俗表現のリアルさが賞賛されるケースはあまりないように思うのだけれど、こういう「今」の空気を文章で出せるってなかなかの技巧ではなかろうか。
物語はある大晦日の夜から始まる。四者四様の理由でこの世に絶望した輩が自殺の名所であるアパートの屋上で鉢合わせ、飛び降りの順番を巡って諍いを起こすという、ナンセンスなんだかシュールなんだか、とにかくイギリス風の皮肉っぽい笑いの要素が満載の開幕だ。
スキャンダルで失脚したテレビ司会者、言動がぶっ飛んだ美大生、植物人間の息子の介護に疲れた敬虔で純情おばちゃんに、夢やぶれたアメリカ人のバンドマン。
本来ならばその人生の道筋が交わることはありえなかったであろうそんな四人が、「大晦日に飛び降り自殺を考えた」という奇妙な共通点によって小さなコミュニティを形成する。しかし、その結びつきはゆるい。そこに全幅の信頼や、理解、同情、共感といったセンチメンタリズムはほとんどなくて、本人たちにもよくわからない磁力によってなんとなく仲間になっていくのである。
例えば『陽気なギャングが地球を回す』では、もともと赤の他人だった四人が強盗行為によって連帯する様が描かれ、読者が共犯者意識や内輪感というような彼らの親しさに愉悦を覚えるような形式になっていた。
ところが、この作品に於いて四人はいつまでもバラバラである。誰かと誰かはずっと口論しているし、四人でいたから何かがうまくいくということも特にない。彼らは仲間でありながら、飽くまで一人ひとりなのだ。
四人でいることがもたらす唯一の変化が、もうどこにも行けないし行きたくないという各人の意思に関わらず、何故かいつのまにかどこかへ動いていってしまうということ。そしてこの「いつのまになんか動いている」というのは、この物語自体の進み方でもある。
実際、大晦日に物語が始まると書いたが、その後の物語はものすごくとりとめがない。これも非常に現代イギリス的だなあと思うのだが、物語の進む先に、到達すべきゴールが設けられていないのだ。
こういう時系列でこういう事件があってそれが伏線になってこうつながる、というルート設定がない。ぼやーっとした四人の生活をぼやーっと追う、演出がまるでないリアリティショーのような手触りのストーリー展開なのである。
しかし、よくよく考えてみれば、自殺せんとした人間を描くにあたってきれいな結末がありえないのは当然だ。
四人が自殺を考えたのには理由がある。例えばモーリーン。彼女が飛び降りるのをやめたからと言って、植物人間の息子が目を覚ます訳ではないし、また介護に明け暮れる日々に戻るだけだ。
この話は、そういう事実を、何度も繰り返し、そして克明につきつける。
自殺をやめました、また生き直そうと思いました、人生つらいけど前を向いていこう、めでたしめでたし、というご都合主義に正面きってNOと言うその大胆さもまた、イギリス人の人生哲学を強く感じさせるものだ。
では、この物語は一体何なのかというと、前述のとおり、本人がどう思っていようが何を考えていようが世界は進むのだということを説いているのだと思う。しかもだいぶネガティヴな口調で。
登山で本当にしんどいのは下りだという。下り坂を走らずに降りるのは膝に負担がかかる。でも、いちど下り始めてしまった以上、立ち止まることは許されない。慣性の法則にしたがって、ただただ下る。
それと同じで、人生はつまりA Long Way Downなのだ。
四人にとっての人生の課題は、ほとんど何も解決されない。(問題の解決をもってして話を帰結させないのは、イギリス映画でもよく見られるパターンだ) 生きづらさはこれからもずっと彼らにつきまとうだろう。それでも、四人は生きていく。希望があるからではない。生きがいを再発見したからでもない。彼らは、ただ、「自殺できなかった」のだ。
自殺に取材する文学作品は数多くあるが、こういう視点で生きることの覚悟を描く小説は珍しいと思う。
ただ、最所訳に引っかかるところと、イギリスの大衆文化を知らなければ笑えない箇所が多くあって、万人には勧めづらい一冊。
かつての翻訳小説のように、現代小説も用語解説を入れてくれればいいのに。
さておき映画化も決まっているとのことなので、公開の暁には是非観てみたい。