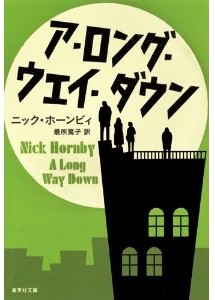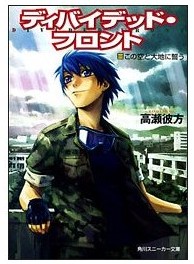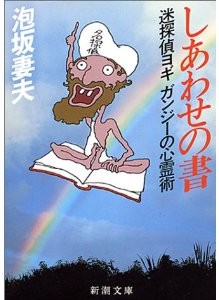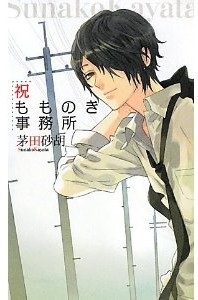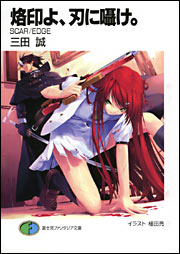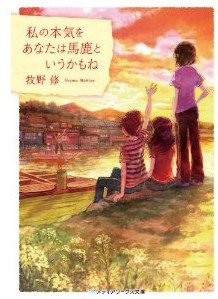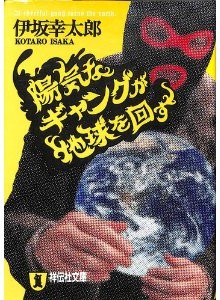なにかとばたばたしていてしばらく本の感想を書く暇が持てず、このままでは読んだ本を忘れていきそうなのでとりあえず簡略版をば。
短く書けそうなものだけなんとか…骨太な作品は手が回らなかったのでまた後日。
アン・マキャフリー 『だれも猫には気づかない』 創元推理文庫、2003年

懲りずにまた猫もの。たまたまタイトルに惹かれて手に取ったのだが、読了後、積ん読している『歌う船』の著者だと知って驚いた。
中世的な世界を舞台にした勧善懲悪ファンタジーで、ドキドキやハラハラは特になく最初から最後までベタなストーリー。
タイトルに反して、猫のニフィは王宮中から一目置かれている超賢猫で、
著者がとにかくこの子をいかに美しくエレガントに描くかに苦心した感がひしひし伝わる。
ただ、かと言ってそれほど印象的な猫エピソードがある訳でもなし…特筆すべき感想も特になく、まあまあな感触。
高瀬彼方 『ディバイデッド・フロント 3』 角川スニーカー文庫、2005年
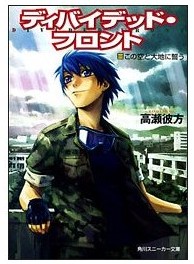
ページをめくる手が止まらなかった。一行一行が波のように胸に迫り、読み終えた後に途方も無い充足感がもたらされた。
2014年読んで良かった本ランキングを作るとしたら、恐らく上位に食い込んでくると思う。
前作が続刊としてあまりにも見事で、物語の輪郭と様式を完璧に成立させていたので、最終巻ではどうまとめられるのかという点だけに集中できたのも良かった。
前作の感想で生駒だけが一人称パートがなかったことを指摘したのだが、今回のプロローグでは涙必至の演出が。そんなのずるいよ生駒隊長…!
こんな特殊な舞台設定で普通なラブコメとか無理ありすぎでしょ、という所感を初めに抱いたというのも、蓋を開けてみればただ高瀬彼方の手のひらで転がされていただけだったという。
普通な訳がない。普通にできる訳がない。それでも普通であり続けようと抗う戦士たちの生き様と、それをあざ笑うかのような現状の厳しさがこのシリーズの核なのだと思う。
ハッピーエンドではないが、しかしつらいだけではない。キャラクターの途中参入も効果的で、最後まで失速せず、すばらしい完結だった。
泡坂妻夫 『しあわせの書』 新潮文庫、1987年
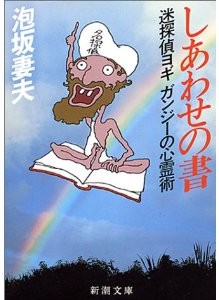
どこの書店に行ってもけたたましく煽情的なポップと共に平積みしてあって、そんなに言うなら!と購入。
いちばんの肝であるトリックは確かにわかると面白いのだが、そのトリックによって生まれる制限のためか、物語自体の引力はいまひとつ。
泡坂作品ならもっと面白いのがいくらでもあるので、何故これがここまで”売れて”いるのかはいまいちわからなかった。
本格推理小説と言えるかどうかはやや疑問が残るが、電車の中でさらっと読む分にはよい。
栗本薫 『優しい密室』 講談社、1981年

十代の時に読んでおけばよかったという激しい悔恨に襲われた。あの頃の自分にとって一体どれほどの救いになりえただろう。
青春小説の名作と言われることが多いこの作品だが、”みんな”の側に入れない女子高生の気持ちがほんとうによく描かれている。
エモーショナルな方向へ加速していくと思いきや、探偵ものミステリとしてもレベルが高く保たれていて、いかにも名作然とした名作。
栗本薫はもう少しドロドロしたものしか知らなかったので、このテイストは意外だった。
女性にお薦めの本を聞かれたときの正答ストック入り。
楡井亜木子『はじまりの空』を思い出した。
茅田砂胡 『祝もものき事務所』 中央公論社、2012年
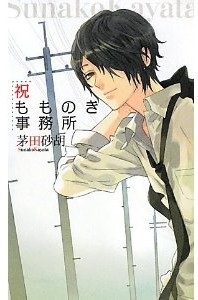
チャラいなー。スーパーライトだなー。という印象。
なんとなく読み覚えのある感覚があってよくよく考えていたんだけれど、創作SSのノリなんだと合点がいった。
リーダビリティは高く、あまり引っかかることもなくさらさら読めるのだがいかんせん薄味すぎてなんとも言えない。
タイプの違う二人の美青年脇役が、お互いに「かわいい」と言い合ってるのが不意打ちな萌えで唯一よかったかなあ。伝わる人だけに伝わるたとえ方をすると、『ミスターフルスイング』の司馬・兎丸みたいな感じ。
シリーズ第三作目はこの子たちメインの短篇集らしいので、気が向いたら読むかも。
三田誠 『烙印よ、刃に囁け。―SCAR/EDGE』 富士見ファンタジア文庫、2004年
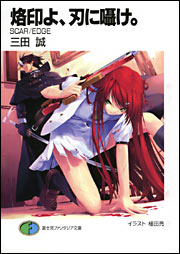
1/4読んだあたりで「あ、これダメな感じのだ」と悟り、結局面白さを見いだせないまま読了。
主人公が主人公たる意義がイマイチ見いだせず、アクションシーンもあまりイメージ喚起力があるものではない。
作中で異口同音に狂ってると形容される悪役の親玉も、『マルドゥック・スクランブル』のボイルドを思えばかわいらしいものだ。
異能力者同士のバトル、親のいない高校生、学園生活、ボーイ・ミーツ・ガール、過去の因縁、とラノベの定番がいっぱい詰め込まれているのだが、では他のラノベ作品と一線を画す作品ならではの魅力は聞かれるとちょっと返事に窮すると思う。
ラノベ修行の道、未だ一進一退。
牧野修 『私の本気をあなたは馬鹿というかもね』 メディアワークス文庫、2014年
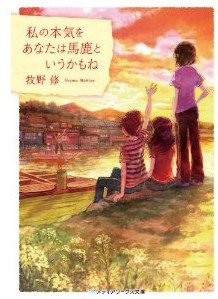
大大大大好きな森奈津子先生がTwitterで宣伝してらした、出たてほやほやのラノベ!
女の子の描き方が魅力的すぎてくらくらする。一人ひとりは勿論、メイン三人が揃ってわいわいきゃっきゃやっているシーンはページから星が飛び出してきそうなくらいキラッキラで涙が出そうになった。
ストーリー自体はかなりどっしりとしていて、背景の深淵さが余計に少女たちの輝きを引き立てているようにも思う。
悪い奴がとっちめられて世界が変わってバンザイめでたしおしまい!ではなく、日々はいつまでも続いていくのだということを示唆する結末には胸が詰まった。
でも読後感は悪くないんだよなあ…少女たちの与えてくれる希望がほんとうに大きくて、元気の出る一冊。
できたらまたちゃんと感想を書きたいと思う。
伊坂幸太郎 『陽気なギャングが地球を回す』 祥伝社文庫、2006年
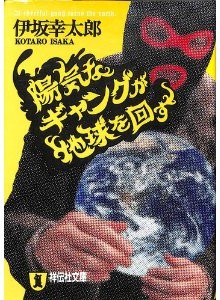
地震の揺れで自部屋の本棚から転がり落ちたので、折角なら、ということで再読。もう8年前の作品であることに驚くと同時に、伊坂ブームってまだ10年か、ということにも驚き。
伊坂作品はかなり久々だったが、語り口の軽妙洒脱な印象は今でも変わらなかった。
一口で言って、面白い。もうほんとこれに尽きる。ジ・エンタメ。嗚呼愉快。
ストーリー自体はそれほどなのだが、こういう仕上がり感にするにはあまり濃厚すぎる筋でもダメそうだし、結局バランスとしてはこれくらがいちばんいいのだろう。
伊坂作品の登場キャラクターにはどことなく類型があるように思うが、『重力ピエロ』の弟くんや久遠のキャラデザには著者の深い愛情を感じる。こういう男の子が、伊坂幸太郎にとってある種の理想形なんだろうか?