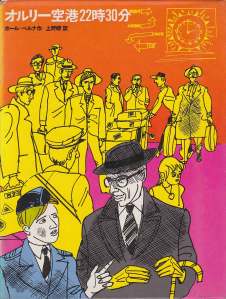カドカワKindle三発目。そして、三度目の正直。楽しめた。楽しめたよ!やった~!
前二作でハードルが地面すれすれに下がっていたことも多少作用しているだろうが、それを差し引いても、申し分なくおもしろいと言える。
Kindleアプリでの読みづらさも今まででいちばん少なく感じた。なぜだろうと思案していたのだがなんのことはない、改行が少なく、会話と地の文のバランスが適当で、端的に言うと一般的な文芸書のような紙面だからだ。
つまり、下半分が白いタイプの作品は電子書籍との相性が悪いということであり、ラノベをKindleでザクザク読もう作戦は早晩頓挫した。
主人公は男子中学生の牧生。彼がつるんでいる幼馴染の男女四人グループと、突然その輪の中に飛び込んできた性格の悪い美少女、りあの五人を中心に話が進んでいく。五人のキャラクターは、描写の細かさに差こそあれ、皆きちんと性格が立っていて魅力的である。特に、牧生とりあのメイン二人がかわいくて、かなり寄り添った気持ちで読むことができた。
超絶美少女でありながら悪魔と呼ばれるほど周りを顧みないりあは、ラノベのヒロインにありがちな造形ではある。しかし、話が進めば進むほど、数々の問題行動の背景に彼女のどんな心情があったのかが明かされていき、ただのわがまま地雷女ではないりあが見えてくる。そして牧生という尋常ならざる器の持ち主がそんなりあを受け入れていくさまに、大きな救済とカタルシスを覚えた。
学校では単なるトラブルメーカーでしかないりあが、牧生と二人きりの時は違う顔を見せる。ともすればあざとすぎてうんざりするようなこの設定が、この作品ではとても自然で且つ効果的に使われていて、上手いなあと感心しきりだった。
牧生とりあの交流が深まるのと同時進行で、いつまでも昔のままのふりをしてきた幼馴染四人の関係性にも変化が訪れる。このあたりの人物の絡め方にもリアリティがあって読んでいて楽しい。決定的な出来事があって完璧に断裂するとかではなく、いつのまにか亀裂が入っていて、そこから段々と形がゆがんでいくような十代の友情をよく捉えていると思う。そして、各人がそれぞれの取捨選択を強いられる中、牧生はりあルートを選ぶのである。
「でも、誰だってあると思うんだ。外から見たら、格好悪い、くだらないかもしれないけど、自分には、すごく大切で、バカにされたくないものって」
この牧生の言葉に代表されるような、個々にとってのかけがえのないものを理解することは至難の業だ。それがなければ人間関係は成り立たないというのに。
中学生である牧生たちがそれを外部の無理解から守りぬくことは更に困難を極める。しかし、りあという愛すべきヒロインと出会い、また牧生という得難きヒーローと出会い、二人は互いに互いを守ろうと必死に足掻き始める。
共に過ごした時間の長さが幼馴染同士の絆ならば、牧生とりあのそれは工作という趣味だ。牧生はガンプラ好きで、りあは小さな箱庭を作っている。二人とも特別な技術がある訳ではなく作品は稚拙なのだが、それがまた二人の若さや迷いを象徴しているかのようだった。
クライマックスでは疾走感がぐっと増し、伏線が一気に回収されていく。謎がどんどん解けていくと同時にりあを縛っていたものが解かれていく、という構成はほんとうに快感だった。
そして、牧生とりあの出会いが、偶然ではなく必然によって決められた「運命」だったことがわかる時、この物語の美しさに思わずぐっとくるのである。
「……怖いけど、牧生が一緒なら」
でもいまは、おれが一緒だから。
嗚呼、なんというピュアネス…。ため息が出るほどいじらしいジュブナイル小説は、秋の疲れた心にしみじみ染みた。