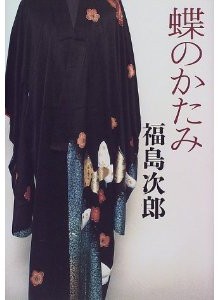ホモセクシュアリティと正面きって向かい合った、冷たさと熱さを併せ持つ文芸作品である。
本作品或いは福島次郎という作家本人について、しばしば「芥川賞候補となり、受賞は逃したものの石原慎太郎と宮本輝に絶賛された」という文言に遭遇する。と言うより、それ以外の説明をほとんど見かけたことがない。
しかし、石原・宮本両氏のお眼鏡に適ったという事実は果たしてその文学的価値を約束するものなのだろうか?
畑がまるで違う例えだが、かのベンゲルが認めたというまことしやかな評判でつかの間の寵児となった伊藤翔が結局どんなサッカー選手になったかを考えると、こういった箔付けはいかがなものかと思ってしまうのである。
かと言って、この作品の価値を認めない訳ではない。むしろ、あまりにも秀でた作品だからこそ、もっと視野の広い評価を与えられるべきだと思う。
初老にさしかかった同性愛者の兄弟を主人公に据え、ホモフォビアのきらいがある兄と、享楽を追い求める淋しき弟の不器用でいびつな交流を描く表題作は非常に味わい深い。
戦後の日本でセクシャルマイノリティとして生きること、その可笑しさ、気楽さ、悲しさが絶妙な筆致で描かれ、近年の高齢者小説とはひと味違う世界が展開される。
しかしそれ以上に、併録された『バスタオル』がとにかく素晴らしい。日本文学における同性愛小説(というカテゴライズはちょっと不本意だけれど)のひとつの完成形だという強い確信を得た。
十代の頃から自分の性的指向を自覚している主人公・兵藤は、青春期の絶望と挫折を経て田舎町での教職というポジションにようよう辿り着く。無聊をかこつような日々の中で、墨田という一人の学生との出会いがあり、互いに対して抱く感情が何であるかを意識しないまま、なし崩し的な肉体関係を持つようになる。
後ろめたさや躊躇、羞恥がだんだんと押し流されていき、ふたりがおそるおそる心を通わせていく…この過程の描写が実に愛おしい。
身体の関係が先行したふたりがしかし少しずつ恋を認めていく。その臆病で繊細な様子はきゅんきゅん必至。
兵藤が墨田にのめりこみ、また墨田も兵藤にどんどん身をまかせていくさまは、恋愛小説の粋が詰め込まれており甘酸っぱさがひしひしと胸に迫る。
気がつけばどうしようもなく好き合ってしまっていたという、なんともかわいらしいカップルなのだが、作中で兵藤が自嘲するとおり、悲しいかなその関係に未来はない。男女間の事情であればいずれ愛や結婚という美しい帰結を迎えたであろう二人の思慕は、同性同士であるがために宙ぶらりんに彷徨うばかりなのである。世知辛いなあ。
陶酔している間はいかにも崇高に思えた愛の本質を、情事に使っていた汚いバスタオルに重ね合わせるクライマックスは、とてもエモーショナルで叙情的だ。
兵藤は、そのバスタオルを洗わない。作中では怠惰で洗わなかったという表現にとどまっているが、実際彼はバスタオルに染み付いた”もの”を洗い流すことなどできなかったのだと思う。
教師と生徒という背徳の関係性、どうしても表出したがる自分の恋情、そして墨田に対する強い執着。
兵藤がどうしても認められず隠さずにはいられなかったそれらが、洗われないバスタオルという小道具によってあまりにも雄弁に語られるのである。
恋愛小説には苦味がつきものである。
『バスタオル』においてが福島次郎が呈したのは、甘みと苦味が絶妙に交じり合う恋愛を描く一級の文学的技巧であった。
一方で、屈折した時代・環境・人生から恋愛市場とは距離を置いた同性愛者の生き方を描く『蝶のかたみ』も、彼の作家としての慧眼と力量を確かに感じさせる名中編である。
これほどまでに人間を描くのに長けた作家の魅力を、大御所作家の推薦だけで片付けてしまうのは、やはりどうにももったいないと痛感した。